戊 辰 の 役 / 殉 難 者
[戻る]
[TOP]
[行く]
[遊ぶ]
[知る]
[メニュー]
[大窪山墓地(東麓)]
[大窪山墓地(西麓)] .
大 窪 山 墓 地 (中央)

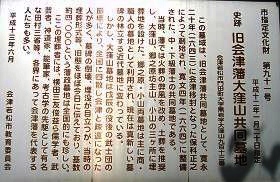
「家世実記 巻之二十三、
巻之二十五」
「新編会津風土記」
(資料提供) 栗城英雄 氏「会津先賢者の墓石を訪ねて/栗城訪霊著」 .

高津豊太郎
八郎の伜。
朱雀士中三番隊/原田隊。
慶応4(1868)年8月29日、融通寺町で戦死。
19歳。
「義賢院殿信誉明道居士」
「会津長命寺裏 進撃の節 戦死」

主税は通称で、諱が常忠。
常徳の養子。 山川常道の子。
若年寄。白河口副総督。
慶応4(1868)年5月1日、磐城/白河稲荷山で戦死。
22歳。 「常忠霊神」
墓碑は、昭和58(1983)年夏、建立。
ここは首塚で、青山霊園に合祀とのこと。
激戦中のため、従者/板倉和泉が首を切り落として持ち帰ったという。
海老名季昌とパリ万博に派遣され、幕府の命令によりロシアを含む欧州も歴訪。
将来を嘱望される若者の1人であった。
| |
通称/主税。 江戸詰家老。
「江戸・三家老」と称された名家老の一人。
(水戸藩/武田耕雲斎、宇都宮藩/間瀬和三郎)
元治元(1864)年8月7日、会津で病没。数え67歳。 |
 |
| |
元治元(1864)年7月19日、蛤御門の戦いで大活躍。
戦後は、大塩村に隠れ住む。
思案橋事件の中根米七を、自邸に匿ってもいる。
後に 私立「日新館」を旧藩士らと創立し教授に就任。 |
 |

伊藤光隆
慶応4(1868)年8月23日、戸ノ口原で戦死。
20歳。
部隊、系累など詳細不詳。
「此君戸ノ口原而戦死 葬彼地 行年二十歳」 とある。

高橋清左ヱ門
善太郎の祖父。
隠居組。
慶応4(1868)年8月23日、南町口郭門で戦死。
(南町の自宅で自刃とも)。
73歳。
「義善院了達日明居士」

入江政徳
.
通称 : 藤三郎。
先代/入江藤三郎の嫡男。
戊辰の役で戦死とされる。
(庄兵衛ならば、
進撃隊/小室隊組頭、8月23日に天神橋で戦死、53歳)

中野半三郎遥拝碑
.
理八郎の伜。
遊撃隊/遠山隊小隊頭(差図役とも)。
慶応4(1868)年閏4月25日、磐城/白河で戦死。
25歳。
「眞輝神霊」
墓は、常宣寺にある。
※ 併記の五郎は、明治11年9月8日、横浜で病死。 「邦彦神霊」

中野克江
.
業助の伜。
大砲士中二番千葉隊。
慶応4(1868)年8月24日、本一ノ丁 (城中とも) で戦死。
26歳。
「義勇神霊」
墓は、「勝江」とある。

通称は与八。 惣五郎常利の子、良助の父。
宝蔵院流槍術師範。 和歌にも長じており和学所師範でもあった。
慶応4(1868)年8月23日、桂林寺町で戦死。 67歳。
戦後に長男や門人たちが遺体を捜すも見つからず、菩提寺に遺詠を埋め、旧邸内の庭石を遥拝石にした。
「晧月院覺譽涼齋居士」
現在の墓標は、昭和58(1983)年7月1日建立。
野矢常方翁拝石は大運寺、顕彰碑が諏方神社にある。
自宅近くの桂林寺町口郭門で、敵兵1人を十文字槍で仕留めるも、銃弾を浴び戦死した。
槍先には、一首の歌が結び付けられていたという。
弓矢とる 身にこそ知らぬ 時ありて ちるを盛りの 山桜花
後の教科書「修身」に常方の歌が載り、全国的に知られることとなる。
君がため 散れと教えて 己まず 嵐にむかう 桜井の里

服部栄
.
別撰組/春日隊組頭。
慶応4(1868)年8月29日、長命寺裏で負傷し、
明治2(1869)年7月、井手村で死去。
26歳。
「尚正神霊」

下條郷助
.
げじょう。
求馬の父。
隠居組。
戊辰(1868)年9月16日、城内で被弾し、10月8日に御山で死去。
69歳。

永岡久命之墓
永岡久茂の遺品を埋葬したと伝えられる。
戦後、久茂は斗南藩で小参事として活躍するも、思案橋事件に関与。
明治10(1877)年1月12日、鍛冶屋橋牢で獄死。 38歳。
捕縛時の傷が原因との発表だが、遺体損傷がひどく拷問による虐殺と云われる。
台東区浅草今戸町の称福寺に埋葬される。
区画整理のため源慶寺に改葬されたが、現在は行方不明。
浮州七郎が生前に「我に益する三友あり 一は永岡久茂の“智”、二は米澤昌平の“直” 三は高木友之進の“勇” 是れなり 我 平生これを慕って及ばず」と語るほどの人物であった。

牧原奇平
.
牧原一郎の弟。
郡奉行。
慶応4(1868)年8月23日、強清水で戦死 (負傷し戦えなくなり自刃)。
戸の口原が破られるの責にて自刃とも。
62歳。
「直義神霊」
主力部隊は日光口・長岡口などの国境に布陣しており、鶴ヶ城下には老人と子供しか残っていなかった。 主力部隊が帰城するまで戸の口で迎撃すべく、急ごしらえの農民、僧侶、神官、相撲取りたちを率いて戸の口に布陣した。
しかし、2千数百ほどの敵兵に対して、戦いに不慣れな4百名ほどの貧弱な装備の兵では、結果は明らかであった。
戸ノ口原古戦場の供養碑の裏面に、「上強清水 牧原奇平他二十一名」の記載はあるが、どの墓に埋葬されているのかは今なお不明である。
次男の牧原勘五郎も、朱雀士中三番原田隊として奮戦するが、8月29日の総出陣において西堀端で戦死した。

荒木半蔵、荒木留吉
.
≪荒木半蔵≫ 久米吉の叔父。
慶応4(1868)年9月8日 (7日とも)、一ノ堰 (飯寺蟻無ノ宮とも) で戦死。
41歳。
≪荒木留吉≫ 久米吉の弟。
江戸大砲隊 (諸生隊諸生組町田隊)。
慶応4(1868)年1月5日、八幡橋下 (枚方関門とも) で戦死。
19歳。 黒谷慰霊碑に記載。

山寺貢
.
天保8(1837)年、誕生。
目付。
慶応4(1868)年6月12日、磐城/白河古天神で戦死。
31歳。
墓碑は「山田貢」になっている。
 西郷常之進
.
西郷常之進
.
青龍士中一番隊/有賀隊半隊頭。
戊辰(1868)年9月14日、諏方神社で戦死。 45歳。
西郷常次郎 常之進の弟。
第二遊撃隊/井深隊。
慶応4(1868)年6月28日、越後/押立峠で戦死。
(15日に戦死とも、越後/森立峠とも)。 38歳。
 西郷常四郎 常之進・常次郎の弟。
西郷常四郎 常之進・常次郎の弟。
諸生組/佐川隊。
慶応4(1868)年1月5日、淀で戦死。 22歳。
京都/黒谷に慰霊碑がある。
平成5(1993)年11月、新しい墓石.が建立。
[戻る]
[TOP]
[行く]
[遊ぶ]
[知る]
[メニュー]
[大窪山墓地(東麓)]
[大窪山墓地(西麓)]
西郷常之進
.
西郷常四郎 常之進・常次郎の弟。